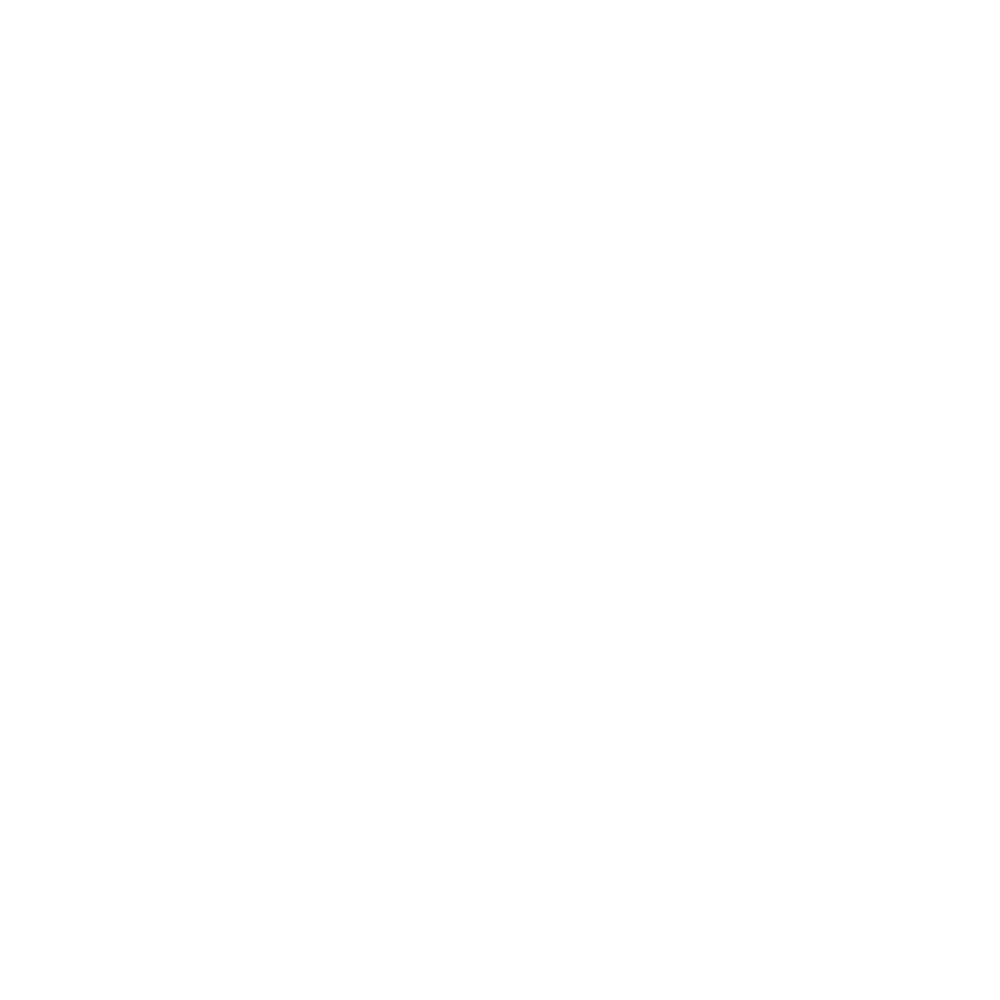チエンマイのソンクラーンに行ってきました(2)
blog No.032 投稿日:2024.08.01
この記事の内容
ソンクラーン สงกรานต์ [sŏŋkraan] ってご存じですか? タイの伝統的な新年を祝う行事のことで、三が日に当たる4月13~15日とその前後数日間は、官公庁、企業等が休みになり(学校は夏休み中)、多くの人が故郷に帰って家族とともに新年をお祝いします。祝福の意味を込めて、お互いに水を掛け合うという風習から「水かけ祭り」などとよばれることもあります。今回(2024年)、初めてソンクラーンを体験してきましたので、その一端をご紹介したいと思います。
・ソンクラーンとは?
・下調べと準備
・ソンクラーン前日(4月12日)
ここまでの前半部分は、前のページ blog031 。これ以後がこのページになります。
・シヒン仏のお出まし
ラーイカム堂からお出まし
伝統と現代技術の融合
信者に引かれて三王の広場まで
・仏像のパレード
ターペー通り
パレードの始まり
シヒン仏の登場
パレードは続く・・・
ワット=プラシン前で見届ける
・そのほかの行事
砂の仏塔
支え木の奉納
様々なコンクール
・チエンマイのソンクラーンを楽しむヒント
チエンマイのソンクラーンに行ってきました(2)
シヒン仏のお出まし
ラーイカム堂からお出まし
※シヒン仏の説明(下の項目)↓↓
ソンクラーン初日の4月13日。元日にあたるこの日に、私がぜひ見たかった仏像のパレードが行われます。
チエンマイの守護仏とされ、パレードの主役となる「シヒン仏(พระพุทธสิหิงค์ [phráphúttha sìhĭŋ/ プラプッタ シヒン])にラーイカム堂からのお出ましを懇請する儀式」พิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์อออกจากวิหารลายคำ[phíthĭi aarâatthanaa phráphúttha sìhĭŋ ɔ̀ɔkcàak wíhăan raaikham/ピティー アーラータナー
プラプッタ シヒン オークチャーク ウィハーン ラーイカム] が午前8時30分から行われます。シヒン仏がお堂から外出するのは、年に1回この時のみです。
堂内での儀式が済んだ後、実際にお出ましになるのは午前9時ころと考え、その少し前に、ワット=プラシン วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร [wát phrásĭŋ wɔɔrámahăawíhăan /ワット プラシン ウォーラマハーウィハーン] に着きました。左手奥のラーイカム堂付近は、すでに見物客でいっぱいです。なんとか居場所を確保して待っていると、テント内にいた来賓の皆さんが一斉に、花びらの乗ったお盆を持って立ち上がります。ラッパと太鼓、銅鑼による威厳ある音楽が鳴っていよいよお出ましです。金色のシヒン仏は、光背付きの台車に乗り、人の手で引っ張られてゆっくりと前へ進みます。見物の皆さんが思い思いに近づいて、花や水をかけるので、介添えの人はびしょ濡れ、シヒン仏が座る蓮華座から腰の辺りまで花で埋まりそうです。
伝統と現代技術の融合
前に高さ4メートルほどの金色の立派な山車が用意されています。なるほど、シヒン仏はこの山車に乗って街をパレードするようです。でも、どうやって重い仏像を山車に乗せるのでしょう?
見ると、山車には階段状のリフトかコンベアのような装置が取り付けられています。台車をぎりぎりまでリフトに寄せて、数人がかりでシヒン仏を持ち上げ(実際には重くて、少しひきずっています)、リフトの台座に乗せます。仏像の腰にシートベルトが締められました。そしてゆっくりゆっくり、リフトを動かして山車の上部まで持ち上げます。仏像がリフトに乗って登っていくのはなかなかシュールな光景です。アナウンスの男性は「伝統と現代の技術の融合です」とうまいこと言っていました。
信者に引かれて三王の広場まで


もう一台、やや小ぶりな山車があり、シヒン仏より小さな仏像が乗っていました。小さい山車がまず動き始めます。寺院の正門の外へ移動し、シヒン仏を迎えることにしました。ご住職が乗った輿を先頭に、数十人の僧たち、続いて小さい山車がやってきます。そして、大きな歓声とともに、シヒン仏の大きな山車がやってきました。
シヒン仏と一緒に、仏像や天蓋を支える白い衣装の若い男性が2人、山車に乗っています。銅鑼の音に鼓舞されるように、たくさんの人が山車についた縄を引っ張ります。沿道で出迎えるたくさんの人は皆、仏像に水をかけて祝福します。白い衣装の男性に合図すれば、手に持っているココナツのひしゃくを差し出してくれるので、そこに水を注げば、シヒン仏にかけてくれます。
パレードと一緒に歩いてみました。およそ30分で三王の広場に到着しました。到着後は意外にあっけなく、儀式もないまま、小さい仏像はトラックに乗せられ、ワット=プラシン方面へ帰って行きました。シヒン仏の大きな山車は山車ごとトラックに牽引され、あっという間に走り去ってしまいました。午後のパレードの出発点に行ったのでしょう。




参考:英国ワット=プラシンHP
仏像のパレード
ターペー通り


「シヒン仏と重要な仏像のパレード」ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ และพระพุทธรูปสำคัญ [khabuanhɛ̀ɛ phráphúttha sìhĭŋ lɛ̀ʔ phráphúttharûup sămkhan/ カブアンヘー プラプッタ シヒン レェ プラプッタループサムカン] は、市役所のHPによれば、午後2時9分、旧市街から1.5kmほど東(鉄道駅方向)のサンパーコーイ交差点 สี่แยกสันป่าข่อย [sìiyɛ̂ɛk sănpàakɔ̀ɔi/ スィーイェーク サンパーコーイ] を出発し、終点のワット=プラシンまで、おそらくずっと直進するようです。途中のターペー通り ถนนท่าแพ [thanŏn thâaphɛɛ/タノン ターペェー] で見ることにしました。なお、TAT Chiangmai のFacebookでは午後3時9分出発となっていましたが、早い時間の方に合わせて、午後2時ころにはターペー通りに着きました。
すでにターペー通りの西半分が車両通行止めになっており、あちこちで水のかけ合いが行われていました。水鉄砲を持って歩いている人に、道ばたからバケツやホースで水を浴びせています。おまけに、チエンマイ市役所水道局の放水車がミストを撒いているので、少し歩くだけで全身ずぶ濡れになりましたが、とても暑いのでかえって心地よいくらいです。Raming Tea House(チーク材の美しい建物をリノベしたカフェ、ソンクラーン期間は休業)の辺りに陣取ってパレードを待ちます。
※水かけについては、こちらに注意点などをまとめておきました。
パレードの始まり


道路が濡れていますが、雨が降ったわけではありません
午後3時ころ、「チエンマイ 新年の行事」ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ [păaweenii pĭimài mʉaŋ ciaŋmài / パーウェーニー ピーマイ ムアン チエンマイ] と書かれた赤い横断幕を持った女性を先頭に、いよいよパレードがやってきました。続いて笛と太鼓と銅鑼の楽隊がやってきます。全員、伝統的な赤い服を着ています。次に「シヒン仏と重要な仏像のパレード」ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ และพระพุทธรูปสำคัญ"[khabuanhɛ̀ɛ phráphúttha sìhĭŋ lɛ́ʔ phráphúttharûup sămkhan/ カブアンヘー プラプッタ シヒン レェ プラプッタループ サムカン] の横断幕と「チエンマイ市役所」เทศบาลนครเชียงใหม่ [thêesabaan nakhɔɔn chiaŋ mài /テーサバーン ナコーン チエンマイ] の横断幕がやってきました。横断幕を持っている女性も音楽隊の男性も、パレードに参加している人はそれぞれ素敵な衣装を身につけているのですが、みんな、放水車のミストと沿道からの祝福の水でびしょびしょです。
シヒン仏の登場
人々の歓声とともに見覚えのある山車がやってきました。ワット=プラシンのシヒン仏の大きな山車です。たくさんの人が駆け寄って、仏像に植物で色と香りをつけた水(説明はこちら)を投げかけたり、男性が差し出すひしゃくに水を入れてかけてもらっています。それぞれの仏像に水をかける時間をとっているのでしょうか。パレードは時々止まって、また前に進みます。
山車の前後には、音楽隊や踊り連の人たちがいて、一緒に練り歩いています。踊りの人は一応、そろいの衣装と音楽に合わせて踊っていますが、昨日、三王の広場やワット=チエンマンで見たようなパフォーマンスではなく、もっと緩い感じで
す。このあと登場する寺院・仏像も同様でした。たぶん、寺院と同じコミュニティに住む人や関係者の方が、この日のために練習して参加しているのでしょう。


ソンクラーンの時、チエンマイの街各地でペットボトルに入って売られていた(500ccで10バーツ)。また、袋入りの花とソムポーイのセットも売られていて、自分で水に混ぜてつくることもできる。
参考:タイ政府芸術局HP
パレードは続く・・・
ワット=プラシンの次に、"พระเสตังคมณี(พระแก้วขาว) และพระศิลา"[phrá sĕetaŋkhamanii (phrá kɛ̂ɛukhău) lɛ́ʔ phrá sìlaa/ プラセータンマニー(プラケーウカーウ)レェ プラシラー] の横断幕がやってきます。ワット=チエンマンに安置される、小さいけれど霊験あらかたとして有名な仏像の名前です。クルーバー=スィーウィチャイ師 ครูบาศรีวิชัย [khruubaa sĭiwíchai](20世紀前半、タイ北部の寺院の修復や復興に活躍した有名な僧)の像に続いて、その2体の仏像が乗る山車がやってきました。しっとり落ち着いたワット=チエンマンの雰囲気とも相まって、私がとても気に入っている仏像で、チエンマイに来ると必ずお参りしています。普段は、お堂にある仏龕の中のガラスケースに入れられているのですが、今日は直接水をかける機会に恵まれました。
仏像の乗った山車を人手で引いていたのは、おそらくプラシンとチエンマンの2寺院だけで、その後の寺院・仏像は、みなピックアップトラックの荷台に仏像を乗せています。行ったことがある寺院も知らない寺院もありますが、仏像に水をかけながらNo13まで見届けました。(たいてい先頭の人や車両が寺院名のプラカードを掲げ、車両には番号を記したゼッケンが貼られています。ゼッケンの数字はタイ文字、寺院名もタイ語だけのことが多いです。)
次にアナウンス用スピーカーを積んだトラックがやってきたので、これで終わりだろうと思いました。パレードはゆっくり進むので、終点のワット=プラシンでもう一度見てやろうと考え、急いで移動することにしました。
※プラセータンマニー仏(プラケーウカーウ仏)とプラシラー仏の説明(下の項目)↓↓
พระเสตังคมณี(พระแก้วขาว) และพระศิลา [phrá sĕetaŋkhamanii (phrá kɛ̂ɛukhău) lɛ́ʔ phrá sìlaa]


ロップブリー ลพบุรี [lópburii] にあったラウォー ละโว้ [láwóo] 国(9世紀ころ、カンボジアの勢力がチャオプラヤー川流域に進出し建てた国)で造られた、高さ約15cmの小さな仏像。言い伝えによれば、仏陀入滅の700年後、天国に赴いたステーワ仙人に対し、インドラ神は白く透明な石で仏像がラウォー国で造られるだろうと言った。地上に戻った仙人はラウォー国で仏像の建造を助け、最後に仏舎利を4か所仏像に埋め込んで完成させたという。
ロップブリーのチャーマテウィー王女 พระนางจามเทวี [phránaaŋ caamateewii/プラナーン チャーマテーウィー] がラムプーン ลำพูน [lamphuun] にあったハリプンチャイ หริภุญชัย [hàríphunchai] 国の支配者として招聘されたとき(西暦663年とされる。8-9世紀の説もある)とき、王女はこの仏像を帯同し、自分の守護仏として祀った。その後、仏暦1824(西暦1281-82)年にハリプンチャイを征服したマンラーイ王は、チエンマイの自分の宮殿にこの仏像を招請し、以後歴代の王によって大切にされてきた。(この宮殿の場所にあるのがワット=チエンマンである。)
【プラシラー】
仏陀入滅の7年7か月7日後、北インド・マガダ国の王は、大洋から石を取り寄せて、右手で象を説き伏せながら托鉢する姿の仏陀の姿と、左側にアーナンダ尊者の像を浮き彫りにした。最後に仏舎利を7つ埋めると、神通力で空中に浮かび上がったため、王は仏像を高い山の断崖に祀った。ここを訪れた3人の長老がこの仏像をパリプンチャイ国に招請したいと願い出て、ランパーン ลำปาง [lamphaaŋ] に安置されることになった。
その後、マンラーイ王の9代目ティローカラート王 พระเจ้าติโลกราช [phrácâo tìlôokkarâat] がチエンマイに招来し、仏暦2019(西暦1476-77年)、自分の宮殿の仏間に安置した。以後、雨をもたらす仏像として大切にされてきた。
参考:仏像を安置する礼拝堂にある説明碑文
石井米雄・監修「タイの事典」同朋舎出版、1993年 David K. Wyatt 「Thailand: A Short History」2nd edition, 2003
ワット=プラシン前で見届ける


パレードを追い越しつつがら、ターペー門 ประตูท่าแพ [pratuu thâaphɛɛ /プラトゥー ターペェー] を越えます。普段は車両が入れないターペー門も、今日は仏像を積んだピックアップトラックが狭い門をギリギリ通過します。10分ほどでワット=プラシンの正門に着きましたが、ターペー通り同様の混雑です。
先ほど見たパレードの後半に追いつきました。ところがパレードはNo13で終わったわけではありませんでした。そのあとも仏像や飾り付けを乗せたピックアップ、踊り手や楽隊が延々と続きます。
寺院によって、タイヤイのキンカラーダンス(説明はこちら)やポーイサーンローン ปอยส่างลอง [pɔɔi sàaŋ lɔɔŋ](子どもが見習僧になる出家式。王侯のように着飾ってお祝いする)の衣装を着た男の子が登場する賑やかなパレード、村の人が総出で来たような素朴なパレード、ミャンマーのポップスで女の子が踊るミャンマー人コミュニティの寺院など、それぞれ見ていて飽きません。そしてパレードは、No50の寺院のあと、ソンクラーンの説話に登場するカビンプロム กบิลพรหม [kabinphrom] 神の頭像を乗せたチエンマイ市役所の山車がしんがりでした。すでに夕方6時をまわっていました。
そのほかの行事
砂の仏塔


(右)ワット=チエンマンの砂の仏塔
色とりどりの長い旗トゥンは、北タイではよく見かけます
ソンクラーンの時期、北タイの寺院に行くと、砂でできた仏塔 เจดีย์ทราย [ceedii saai/チェーディーサーイ] をよく見かけます。この、北タイの風習には、次のようないわれがあります。
北タイでは昔から、仏陀の住む天上界を模して寺院を造りました。仏像を祀る礼拝堂は仏陀のおわす山を表わし、礼拝堂のまわりには天上界の海を示す清浄な白い砂を敷きました。寺院にお参りしたとき、足に砂をつけて外に運び出すのは悪い行いですが、新年に寺院に砂を持って来れば、無病息災と長寿にあずかれると言われます。そこで、北タイの人はソンクラーンの時に寺院に砂を運び入れ、竹を曲げて丸い形にして、砂を入れて仏塔の形に作ります。
今ではこの行事に気軽に参加できます。多くの寺院では砂の山が置いてあるので、そこからバケツで運んで、竹で囲まれた砂の仏塔にかけてください。また、北タイ伝統の旗 ตุง [tuŋ/トゥン] (長細い布や紙でつくられ、十二支・象などがデザインされている飾り旗)を砂の仏塔に刺して飾り付けることもできます。どちらもいくらか寄付をするのが普通です。
参考:タイ国芸術局HP
支え木の奉納


寺院に必ずある菩提樹。仏陀がこの木の下で成道に達したことから、仏教の象徴として大切にされてきました。北タイの寺院に行くと、菩提樹を支えるようにたくさんの金色銀色の木や枝が並べられているのが見られます。この支え木「マイカムサリー」ไม้ค้ำสะหรี [mái khám sarĭi] は、信者たちが、自分の望みがかなうように、自分の人生を支えてくれるように、そして仏教が末永く続くように支えたいという意味を込めて寄進し、菩提樹を支えるように置いたものです。
この風習はソンクラーンの時期に限ったものではありませんが、やはりソンクラーンの時に行う人が多いようです。この時期、多くの寺院で寄進用のマイカムサリーが用意されているので、いくらか寄付して(私はたしか79バーツだった)、菩提樹の根元に置いてみましょう。木に名前や願い事を書けるよう、マジックペンが用意されていることもあります。
参考:チエンマイ大学 北タイ知識の蔵
様々なコンクール


チエンマイ市役所HPから引用しました
北タイの文化を広めて継承するため、ソンクラーン期間中、ターペー門広場において様々な文化的行事・コンクールが行われます。上述した砂の仏塔、飾り旗トゥンのコンクールに加えて、寺院へのお供え飾りやラープ(挽肉入りのサラダ料理)のコンテストも行われていました。また、ステージ上では傘差し自転車美人コンテストもありました。これらの行事は自由に見学できます(ラープは試食もさせてもらえます)。
チエンマイのソンクラーンを楽しむヒント
今後、チエンマイでソンクラーンを体験してみたい方に、私が気づいたヒントを書いておきます。
混雑するので、早めの計画を
外国人観光客はもちろん、故郷に帰るタイ人もたくさんいます。航空機、列車、長距離バス、ホテルなど混み合いますので、早めの計画と準備が必要です。チエンマイをはじめ各都市で様々な行事が催されますので、あらかじめ日時と場所を調べておくと、より楽しめます。
暑さに注意
一番暑い時期になります。とくにチエンマイなど北タイでは日中40℃前後になります。乾燥していますので、日本の夏よりはまだ過ごしやすいとは思いますが、日差しは痛いほどです。無理をせず、熱中症などに十分注意してください。
水かけについて
・水かけに参加したい方は、街のあちこちでいろんな水鉄砲を売っています。私は小さいものを30バーツで買いましたが、観光客向けの露店では、大きなものが400バーツ、500バーツと高く売られていますので、雑貨屋さんやコンビニなどで見かけたら買ってしまいましょう。
・道端や自分の家の前では、ホースや大きな水タンクとバケツを用意して通行人やバイクに水をかけています。水鉄砲と違って、ホースやバケツだとずぶ濡れになります。暑いので気持ちいいくらいですし、直に乾いてしまいます。もちろん、水は祝福の意味でかけられるので怒ってはいけません。
・水鉄砲の水の補給は、大きな水タンクを置いている人にお願いすれば、たいていタダで汲ませてくれます。
・携帯電話、パスポート、財布など濡れてはいけないものは、必ずジップロックにいれておきましょう。首掛け式の携帯電話の防水ケースは、街のあちこちで売っています。
・お堀のそばだと、お堀の水をポンプで汲んで水をかける人がいます。お世辞にもきれいとは言えない水で、市役所なども使わないように言っているようです。なるべく近寄らない方がいいと思います。
北タイの生活文化に興味ある人は・・・
チエンマイ旧市街のほぼ中央、三王の広場の向かい側にある「ラーンナー民俗博物館」Lanna Folklife Centre(หอพื้นถิ่นล้านนา [hɔ̆ɔ phʉ́ʉnthìn láannaa/ホー プーンティン ラーンナー] では、このブログで紹介した、爪踊り、トゥンという旗飾り、砂の仏塔、マイカムサリーなど北タイ(ラーンナー地方)の生活文化がとてもわかりやすく展示、説明してあります。ぜひ、ソンクラーンの前に見学することをおすすめします。
【入場料】90バーツ 【時間】8:30~16:30 【休館】月曜・火曜・ソンクラーン期間