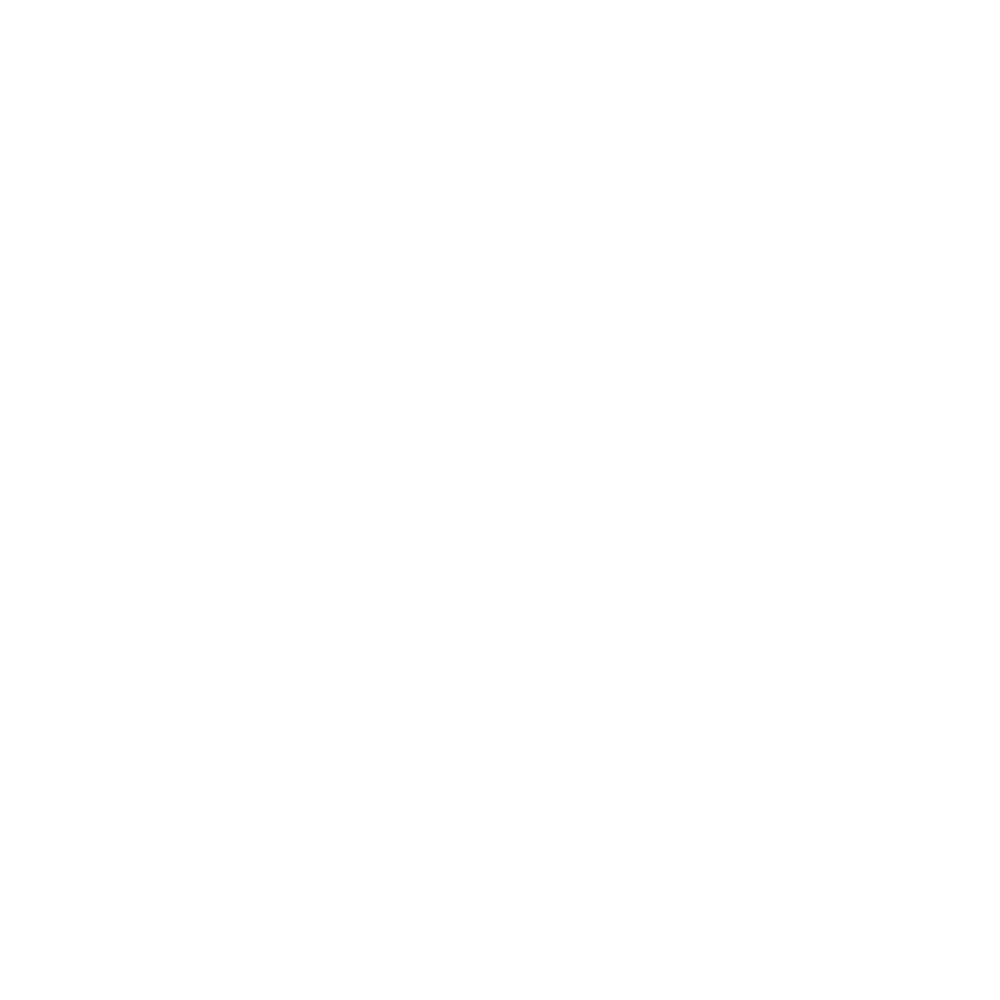日本語のなかのタイ語1
blog No.009 投稿日:2020.07.26
この記事の内容
英語などと違って、タイ語由来のことばが日本語の日常語に入ってきている例は、決して多くはありません。それでもタイ語を学んでいると、ほんの時々ですが、「あっ、これ日本語と同じだ」と思うこともあります。そんなことばの備忘録として、この記事を書いてみました。
・しゃも(軍鶏)
・すんころく(宋胡録、寸古録)
・キンマ(蒟醤)
・今日のことわざ
※以下の文中にはタイ文字が使われていますが、読めなくても全く問題なく理解できます。
日本語のなかのタイ語1
しゃも(軍鶏)
闘鶏は16世紀末以降、当時「シャム」สยาม [sayăam/サヤーム] とよばれていたタイから日本に伝えられたようです。闘鶏に使う鶏「しゃも」は「シャム」から来たことばだとされています。16世紀末といえば、日本は豊臣政権の時代ですが、タイは、隣国ビルマに支配されていたアユッタヤー อยุธยา [ʔàyútthayaa] 王朝の独立を回復したナレースワン大王 พระนเรศวร มหาราช [phráʔ nareesŭan mahăarâat/プラ ナレースワン マハーラート] (在位1590-1605年)の時代でした。そのころ、王都にして一大貿易港だったアユッタヤーには、ヨーロッパ・アジア各国の商人とともに、日本人の商人の居留地(いわゆる日本町)もありました。江戸時代になって幕府が朱印船貿易を進めると、タイと日本の往来も活発になり、日本町も盛期の1620年代には1000~1500人の人口を抱える規模になりました。日本がいわゆる鎖国政策に転じた以降も、アユッタヤーの商船は中国船として長崎に来航していました。タイから鹿皮・錫・蘇木(染料)などの物産とともに、闘鶏も持ち込まれたと推測されます。
なお、アユッタヤー朝のナレースワン大王には、闘鶏に関する次のような逸話が伝わっています。
ビルマ軍がピッサヌロークを占領すると、その領主の子だったナレースワンは、ビルマ国王の養子(実際は人質)としてビルマの都バゴーへ引き取られ、15歳までの6年間、そこで過ごしました。ある日のこと、ナレースワン王子がビルマ王の孫と闘鶏をし、見事勝ちました。面白くないビルマ王の孫は「この囚われの鶏、なかなかやるじゃないか」と皮肉たっぷりに言い放つと、ナレースワン王子は負けじと「この囚われの鶏は、今日のように王宮内の遊びだけで闘うのを禁じられているんだ。国を賭けて闘うっていうのはどうだい?」と言い返したといいます。


(アユッタヤー、ワット=タンミカラート)
すんころく(宋胡録、寸古録)
桃山時代から江戸時代の初期に、タイから日本に輸入された陶磁器のことを、生産地の地名サワンカローク สวรรคโลก [sawănkhá lôok] にちなんで、こう呼びます。タイ語では少し変化して、サンカローク เครื่องสังคโลก [khrʉ̂aŋ săŋkhálôok](khrʉ̂aŋとは、器という意味)と言います。と説明してもご存知でないかもしれません。当時、日本とアユッタヤーとの活発な貿易によってタイからもたらされたすんころくは、独特の渋い色使いやマンゴスチンをかたどった造形が日本の茶人たちに熱狂的に愛好され、おもに香合(こうごう、茶室に焚く香を入れる器)として珍重された焼き物なのです。
現在、スコータイ県北部にサワンカロークという町がありますが、陶磁器の生産が行われたのはそこではありません。アユッタヤーに先立つ13~15世紀に、タイの王都だったスコータイ สุโขทัย [sùkhŏothai]から、北におよそ60km行った場所にシーサッチャナーライ ศรีสัชนาลัย [sĭisàtchanaalai]という古都があります。スコータイ時代には副王が統治する重要な都市で、当時の寺院跡が歴史公園として整備され、スコータイやカムペーンペットとともにユネスコの世界遺産に登録されています。14世紀以降、元代の中国の影響を受けて、この町で陶磁器生産が始まりました。アユッタヤー時代にはサワンカロークと改名され、ここで作られた陶磁器が東南アジア各地や遠く日本まで輸出されました。今も窯跡が保存され、立派な博物館もできています。現在のラッタナコーシン朝のラーマ1世(在位1782-1809年)の時代に、サワンカロークの町は10kmほど南の、現在の場所に移されました。
なお、サワンカロークとは、サワン สวรรค์「天国」+ローク โลก「世界」、つまり天国、天上界という意味です。スワンカロークという表記も見られますがタイ語の発音としては誤りです。おそらくは、サワンをタイ文字のスペルに従ってローマ字化すると swan になることから生じた誤りだと思われます。


キンマ(蒟醤)
タイ語の「キンマを噛む」ということば「キン マーク」กินหมาก [kin màak] に由来しますが、そもそもキンマとは何かについて説明した方がよいですね。
植物のキンマ
マレー半島を中心にインド・東南アジア・台湾にかけて、「キンマを噛む」(英語では betel chewing)という習慣があります。材料は次の3つです。1)ビンロウ(檳榔)というヤシ科植物の実の種(ビンロウジ、檳榔子)を薄く切るか、すり潰したもの 2)貝殻を粉状にした石灰。赤く着色することもある 3)コショウ科の植物の葉
2)を塗った3)に1)を包んで噛むと、清涼感と刺激感が味わえるといいます。砂糖や香辛料などを一緒に包むこともあります。赤くなった唾液と噛んだかすは外に吐き出します。この習慣をタイ語では「キン マーク」というのですが、なぜか日本語では3)の植物自体をキンマと呼ぶようになりました。
タイ語では、ビンロウの実を「マーク」หมาก [ màak]、植物のキンマを「プルー」พลู [phluu] とそれぞれ言います。本来「マーク」は「果実」という広い意味を表しますが、タイでは「キンマを噛む」ことが上流階級から庶民まで愛用され、結納品などにも使われるほど社会的に重要な意味を持ったので、単に「マーク」といえばビンロウジを指し示すようになりました。また「プルー」は地名によく使われていて、たとえばバンコクのバーンラック地区には、ワットスアンプル― วัดสวนพลู [wàt sŭan phluu](キンマ畑寺)という寺院があります。
タイでは、第2次大戦中、プレーク=ピブーンソンクラーム แปลก พิบูลสงคราม [Plɛ̀ɛk Phíbuun sŏŋkhraam] 首相が「キン マーク」の習慣は前近代的という理由で国民に止めるよう勧告して以来、急速に廃れていきました。現在では地方の高齢者以外、習慣的に行っている人はほとんどいません。インド、ミャンマー、インドネシアなどでは今も広く行われていて、道端に血へどに似た赤い唾液がよく落ちています。台湾でもポピュラーで、今のようにコンビニがない時代は、水や缶ビールは「檳榔」の店(商品を並べる冷蔵ガラスケースがある)で買ったものです。一度、飛行機で隣り合わせになった台湾の人からキンマをもらって噛んだことがありましたが、慣れてないせいか、とくに爽快感を感じるものではなかったです。今でも台湾では、街道沿いにキラキラの電飾がまばゆい「檳榔」の店が並んでいて、ガラス張りの店の中に水着の若いお姉さんがいて客寄せをしています。以前はもっと過激な服装をしていましたが、見とれたドライバーが事故を起こすので規制がかかったそうです。
高級漆器としてのキンマ
画像は、東京国立博物館「研究情報アーカイブズ」https://webarchives.tnm.jp/から引用しました

17世紀、タイから伝来した漆器「キンマ」
結納品や客のもてなしなどに使われたことから、ビンロウジやキンマの入れ物やお盆も、銀製品や漆器など高級な芸術品がつくられるようになりました。日本でキンマとよばれる漆器(ないしはその技法)は、香川県漆器工業協同組合のホームページでは室町時代の中期に倭寇が日本にもたらしたとありますが、そのころ(15世紀) 貿易船をさかんにアユッタヤーに送っていた琉球王国経由で日本にやってきた可能性もあるのではないでしょうか。16世紀末以降は、直接アユッタヤーから日本へ送られたと思われますが、やはり茶人が香合として珍重しました。それは、漆面に細かく模様を彫った後、そのくぼみに色漆を埋め込む作業を繰り返し、最後に表面を研ぎ出して仕上げ用の漆を塗るという、たいへん手間のかかるものでした。
今日は、日本とタイとの交流の歴史を物語ることばを紹介してみました。実は、他にも日本語になっているタイ語はありますので、次回紹介したいと思います。
今日のことわざ
แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง (หนูคะนอง)
[mɛɛo mâi yùu, nŭu râarəəŋ(kháʔnɔɔŋ) / メェーオ マイ ユー ヌー ラールーン(カノーン)]
日本語訳:猫がいなけりゃ、ネズミがはしゃぐ
前回の犬に対して、今回は猫 แมว [mɛɛo/メェーオ] のことわざです。さげすまれてきた犬と違い、猫は幸運を呼ぶ動物として昔はどの家でも大切に飼っていたそうです。こんな新聞記事がありました。干ばつに困ったタイのある農村で、雨乞いのための伝統行事をやることになりました。3日間、猫を入れた籠を担いで歩き、村人が次々と水をかけます。その時、猫が嫌がって鳴く声が雨を呼ぶと信じられています。ところが、飼い主は猫をそんな風にされるのが不憫だからでしょう。貸してくれる人がなかなか現れず、1匹のお勤めは1日限りということで何とか貸してもらったそうです。そして猫の鳴き声が天に届いたのでしょうか、見事雨が降ったそうです。(2010年7月24日付朝日新聞の記事)
このことわざは、気兼ねする人やうるさい人がいない間にのんびりくつろぐという意味で、日本では「鬼の居ぬ間に洗濯」ということわざに当たります。
[ 参考文献 ] 冨田竹二郎『タイ日辞典 改訂版』養徳社、1990年;石井米雄監修『タイの事典』同朋舎、1993年;Charnvit Kasetsiri『อยุธยา Discovering Ayutthaya』Toyota Thailand Foundation 他(タイ語)、2003年;岩城雄次郎・斉藤スワニー『タイ語ことわざ用法辞典』大学書林、1998年