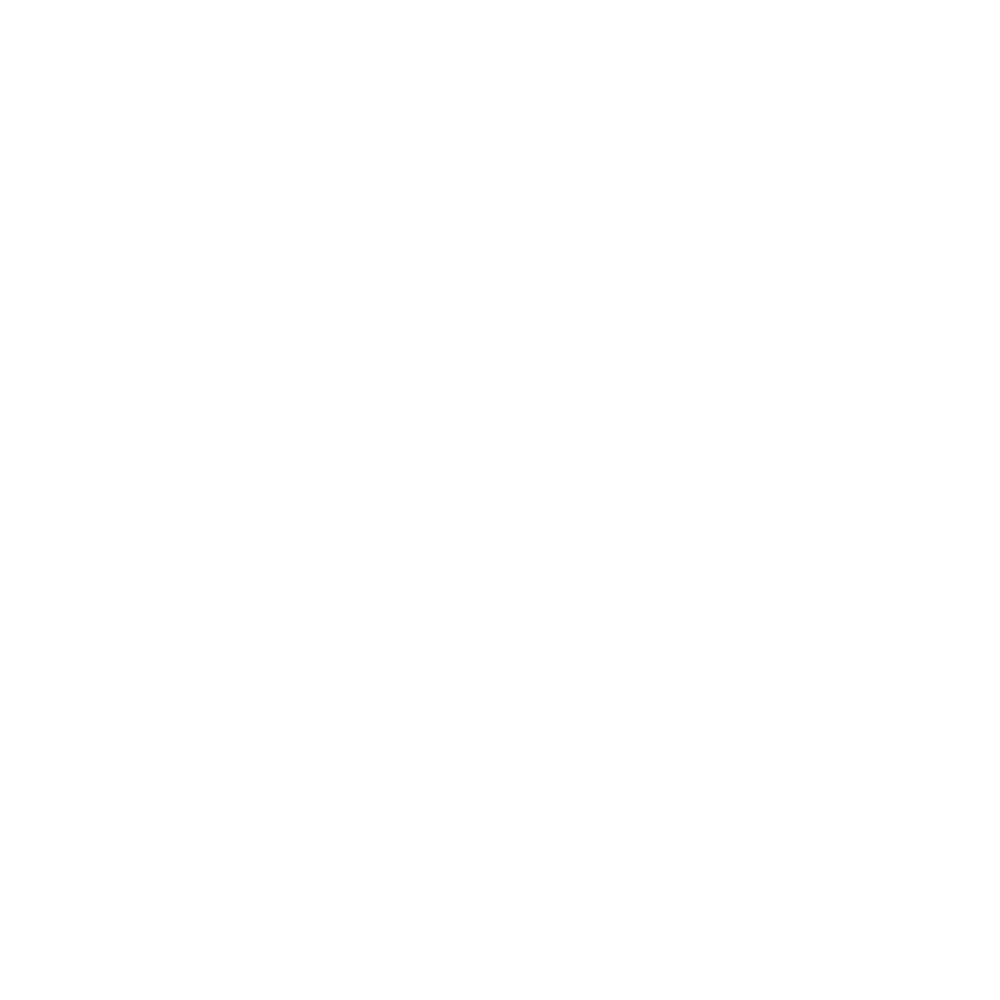日本語のなかのタイ語2
blog No.010 投稿日:2020.08.08
この記事の内容
英語などと違って、タイ語由来のことばが日本語の日常語に入ってきている例は、決して多くはありません。それでもタイ語を学んでいると、ほんの時々ですが、「あっ、これ日本語と同じだ」と思うこともあります。今回は、インド系のことばを思いつくまま並べてみました。
・パーリ語とサンスクリット語
・まか(摩訶)―― มหา [mahăa/マハー]
・ならく(奈落)―― นรก [narók/ナロック]
・タイ語・日本語共通の仏教用語
・今日のことわざ
※以下の文中にはタイ文字が使われていますが、読めなくても全く問題なく理解できます。
日本語のなかのタイ語2
パーリ語とサンスクリット語
タイ語には、インドから伝来したパーリ語とサンスクリット語の借用語が非常に多く、語彙の70%にものぼるとされています。抽象的な概念を表すときに使うことが多いですが、それ以外にも、純タイ語をパーリ・サンスクリット語由来の語句で言い換えると、文語あるいは上品語となります。また新しい概念を表すため、それらの語彙を熟語のように組み合わせて新語を造ることもしばしばあります。ちょうど、日本語における漢語のような役割をしています。
ちなみに、パーリ語とサンスクリット語について簡単に補足をしておきます。いずれも、古代インド北部で使われていた言語です。
サンスクリット語 ภาษาสันสกฤต [phaasăa sănsakrìt/ パーサー サンサクリット] は、ブラフマー神(梵天(ぼんてん))がつくったという伝承から漢語では「梵語」とよばれます。バラモン教の聖典『ヴェーダ』の言語をもとに成立し、北インドで広く使われましたが、しだいに文章語・学術語となりました。古典文学やバラモン・ヒンドゥー教、大乗仏教の経典は、サンスクリット語で書かれており、それらの受容を通じてタイにもたらされました。
パーリ語 ภาษาบาลี [phaasăa baalii/ パーサー バーリー] は、サンスクリット語が口語化・俗語化した言語の1つです。語彙はサンスクリット語と似ていますが、やや砕けた感じになります。タイで最もメジャーな宗教である上座仏教の経典の言語なので、当然多くの語彙がタイ語に取り入れられています。
仏教の受容を通じて日本にもインド起源の語句が入って来ていますので、タイ語と日本語で同じことばが使われているというわけです。
まか(摩訶)―― มหา [mahăa/マハー]
「大いなる」「偉大な」という意味のパーリ・サンスクリット語に由来する語で、摩訶不思議とは「非常に不思議なこと」を意味します。タイ語でも同じ意味で、単語の接頭語(接頭辞)として非常に多く用いられます。มหา [mahăa] がつく単語の例をいくつか挙げてみましょう。
・มหาราช [mahăa râat/ マハー ラート] …「大王」という意味です。ราช [râat] はパーリ・サンスクリット語のラージャ raja 「王」に由来します。日本語でも「マハラジャ」という名前は、バブル期に一世を風靡したディスコをはじめ、インド料理店などでよく使われていますね。ちなみにタイの歴史で มหาราช [mahăa râat] と称されるのは、スコータイ朝のラームカムヘーン大王、アユッタヤー朝のナレースワン大王とナーラーイ大王、トンブリー朝のタークシン大王、現在のラッタナコーシン朝のラーマ1世、チュラーロンコーン大王(ラーマ5世)で、2016年に崩御された先王ラーマ9世も大王と称されることになりました。
・มหาสมุทร [mahăa samùt/ マハー サムット] …สมุทร [samùt]「海」に มหา [mahăa] をつけて「大洋」という意味です。太平洋は มหาสมุทรแปซิฟิก [mahăa samùt pɛɛsifík/ マハー サムット ペェーシフィク] と言います(pɛɛsifík は英語の Pacific です)。「海」を意味する ทะเล [thalee/ タレ―] という単語をご存知かもしれませんが、パーリ・サンスクリット語同士で熟語をつくるというルールになっているので、純タイ語の ทะเล [thalee] に มหา [mahăa] は付きません。
・มหาวิทยาลัย [mahăa wítthayaalai/ マハー ウィッタヤーライ] …「大学」という意味で、มหา [mahăa] + วิทยา [wítthayaa]「学問」+ อาลัย [aalai]「宿る所」の3語から成っています。単に วิทยาลัย [wítthayaalai] というと「高等専門学校」(英語で college と訳している)を意味します。


ならく(奈落)―― นรก [narók/ナロック]
「悪人を連れていく所」という意味のパーリ・サンスクリット語起源のことばで、日本語・タイ語とも「地獄」を表します。日本語では、派生的に「どん底」という意味にも使って「奈落の底に落ちる」と言ったり、「舞台下の空間」を表したりします。
タイの地獄については、スコータイ朝の6代リタイ王 พระเจ้าลิไทย [phráʔcâo lithai/プラチャオ リタイ](在位1346/47-68/74?年)が即位前の1345年に著した『三界経(さんがいきょう)』ไตรภูมิกถา (ไตรภูมิพระร่วง) [traiphuum kathăa (traiphuum phráʔrûaŋ)/トライプーム カタ―(トライプーム プラルアン)] という、タイ語の散文で書かれた最古の仏典(宗教文学とも言える)に描かれています。ちなみにリタイ王は、スリランカから高僧を招き、自ら出家して範を示すなど、あつく上座仏教に帰依しその普及に尽力しました。新たに王都に定めたピッサヌロークに寺院を建立し、その本尊として有名なチンナラート仏 พระพุทธชินราช [phráʔphúttha chinnárâat/プラプッタ チンナラート] (タイで最も美しいとされる仏像)を鋳造させたとも伝えられます(異説あり)。
『三界経』によると、人間が住む世界のはるか地下に八大地獄 มหานรก 8 ขุม [mahăa narók pɛ̀ɛt khŭn/マハーナロック ぺェートクン]があり、不殺生・不偸盗(ちゅうとう)・不邪淫・不妄語・不飲酒(おんじゅ)という在家信者が守るべき五戒 ศีล ห้า [sĭin hâa/シーン ハー]を犯した者が堕ちるといいます。地獄の人たちはすき間なく押し合いへし合い、業火によっていつまでも焼かれ続けます。八大地獄の周りにはそれぞれ16の周辺地獄があり、さらに極悪人が堕ちるという世界中間地獄 โลกันตร์ (โลกันตนรก) [lôokan(lôokanta narók)/ローカン(ローカンタナロック)] を合わせると合計137もの地獄があります。
八大地獄で亡者がどう処罰されるかについて、日本の仏教では具体的に説かれますが、タイの『三界経』では具体的記述はなく、むしろ16の周辺地獄について詳しく書かれています。釜ゆでにされたり、身体をのこぎりで切り刻まれたり、棘だらけの木に登らされたり……。これらの記述をもとに、地獄の様子が寺院の壁画に描かれ、民衆の教化に利用されてきました。タイの寺院を回っていると、時々そんな地獄絵を目にしたり、時には等身大のジオラマに出会うこともあります。地獄のジオラマのある寺院を83か所も訪れて調査した椋橋綾香氏の著書『タイの地獄寺』(青弓社、2018年)は、豊富な写真と合わせて、タイ仏教の説く地獄を知るための絶好のガイドです。タイの地獄のみならず、民衆レベルの仏教に興味のある方にぜひお薦めしたいです。


生前、殺生した者はその動物の頭を持つ人間となって、茹でられたり切り刻まれたりするといいます
タイ語・日本語共通の仏教用語
前項のならく(奈落)のように、タイ語と日本語に共通する、仏教に関する語彙の例を挙げてみます。
ねはん(涅槃)―― นิพพาน [nípphaan/ニッパーン]
ニルヴァーナ(サンスクリット語)、ニッバーナ(パーリ語)に由来します。煩悩の炎がかき消され、苦から解脱した平穏な状態を意味し、この境地に至ることこそが仏教の目的とされます。
あじゃり(阿闍梨)―― อาจารย์ [ʔaacaan/アーチャーン]
パーリ・サンスクリット語のアーチャーリヤに由来し、「他の模範となる者、師匠」という意味です。日本では天台宗・真言宗といった密教の僧侶を指すことが多いようです。タイ語ではもっと広く、「(学問上の)師匠」「(大学の)先生・教授」を意味する日常語になっています。なおタイ語の文字をそのままローマ字化すると aacaary(最後のyは読まない)となって、より日本語の「あじゃり」に近づきます。
はんにゃ(般若)―― ปัญญา [panyaa/パンヤー]
般若というと恐ろしい形相の女の能面を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、本来は「知恵、英知」という意味です。タイ語でもその意味で使います。般若心経の般若も「知恵」という意味です。
びく(比丘)―― ภิกษุ [phíksù/ピックス]
出家した僧侶のことで、タイの仏教では227の戒律を守って修行に打ち込む存在です。尼僧はびくに(比丘尼)―― ภิกษุณี [phíksùnii/ピックス二ー]と言います。タイでは男性しか出家できないので、比丘尼は存在しません。
しゃみ(沙弥)―― สามเณร [săamáneen/サーマネーン]
7歳以上20歳未満の出家者で、10の戒律を守る見習い僧のことです。タイ語では略して เณร [neen] といいます。20歳になると上記の比丘になることができます。
そうぎゃ、さんが(僧伽)―― สงฆ์ [sŏŋ/ソン]
パーリ・サンスクリット語で「仲間、集団」という意味の語に由来し、比丘(出家者)の集団をこういいます。「京都サンガ」とプロサッカーチームの名前にも使われています。比丘のことを「僧侶」ともいいますが、それは僧伽のメンバーという意味です。タイ語でも พระสงฆ์ [phrásŏŋ/プラソン] というと、比丘、僧侶を意味します。口語では単に พระ [phrá] ということが多いようです。
なおタイ語の [sŏŋ] ですが、最後の文字 ฆ์ は、もとのパーリ・サンスクリット語には ฆ [kh]があるけど、タイ語では発音しない(できない)ということを表しています。日本語では「が」「ぎゃ」と発音しています。
だるま(達磨)―― ธรรม [tham/タム]、ธรรมะ [thammá/タムマ]
仏教では仏陀が説いた真実・教えという意味に使い、日本語では「法」と訳します。(インドの僧で中国に禅宗を伝えた達磨大師のダルマもこの意味です。)インドの諸宗教ではもっと多義的に使われるようで、それを受けてか、タイ語では「仏法」以外に「徳・善」「公正・公平・正義」「規則・掟」など広範な意味を持ちます。ธรรมศาสตร์ [thamma sàat/タンマサート] は「法律学」(有名なタンマサート大学の名前にもなっています)、ธรรมเนียม [thamniam/タムニエム] は「習慣、慣例」という意味です。面白いのは ธรรมชาติ [thamma châat/タンマチャート]「自然、天然」ということばです。 ชาติ [ châat] は「生まれ、~の類」という意味なので、「規則性・法則性に従う種類」の生物・無生物が存在する世界が「自然」と考えるのでしょうか。人間は自然の「法則」に逆らう存在とということかもしれません。この辺りのことばは奥が深いですね。


寝仏は、釈迦の入滅・涅槃の姿を表しています
今日のことわざ
ฝากปลา(ย่าง)ไว้กับแมว
[fàak plaa (yâaŋ) wái kàp mɛɛo / ファーク プラー(ヤーン) ワイ カプ メェーオ]
日本語訳:(焼き)魚を猫に預けておく
前回に続いて猫 แมว [mɛɛo/メェーオ] が登場します。日本語の「猫に鰹節」と同じ発想ですね。もちろん、信頼すべきでない人を信用してしまうことを示しています。
同じ意味で「虎に肉を預けておく」「カラスに卵を預けておく」ということわざもあって、この3つの句を同時に使うこともあるそうです。
[ 参考文献 ] 冨田竹二郎『タイ日辞典 改訂版』養徳社、1990年;石井米雄監修『タイの事典』同朋舎、1993年;、椋橋綾香『タイの地獄寺』青弓社、2018年;岩城雄次郎・斉藤スワニー『タイ語ことわざ用法辞典』大学書林、1998年