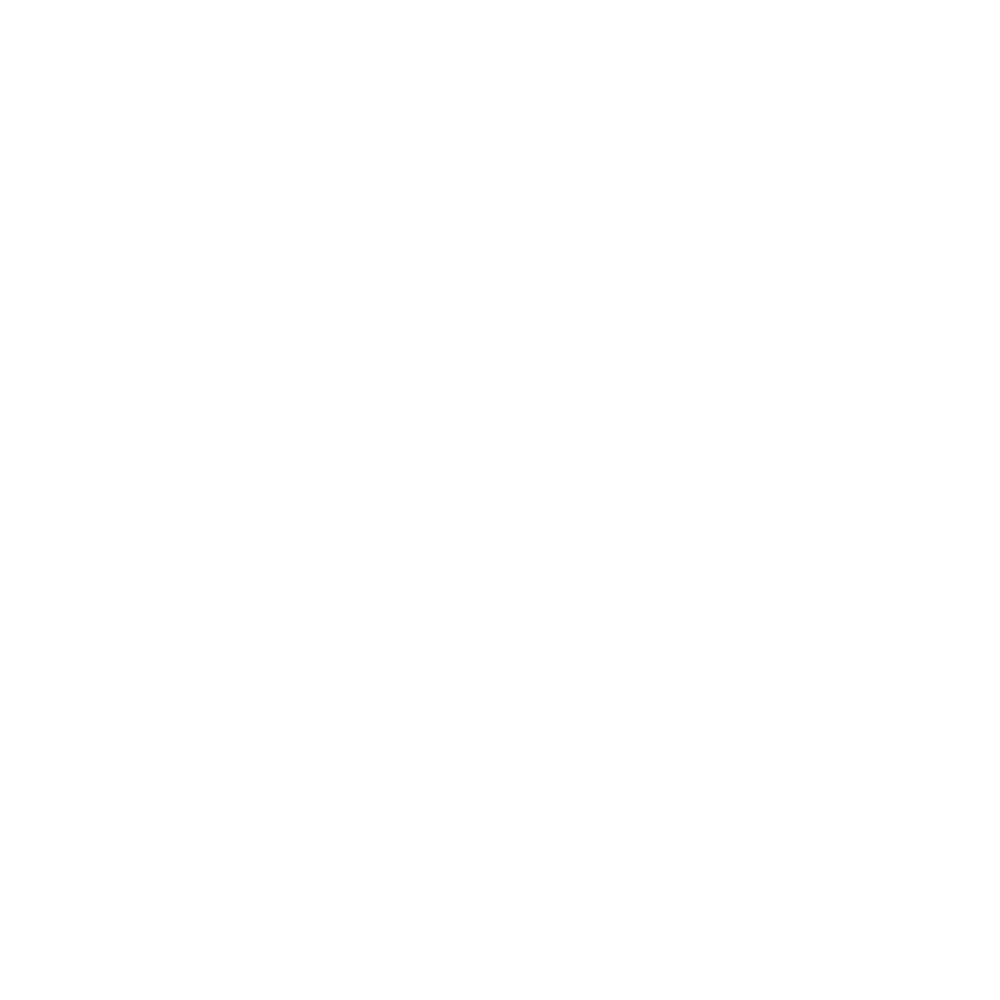旅ときどき単語4 駅名編(2)水にまつわる地名
blog No.029 投稿日:2022.8.13
この記事の内容
どの言語でも語彙力が大切なのは論を待ちません。とくにタイ語は、名詞の性とか動詞の活用といった込み入った文法事項がない分、単語力がより一層重要になります。とは言っても、単語帳とにらめっこしていてもなかなか身につきませんね。
そこで、タイの旅行気分を味わいながら単語を増やす試みをしています。今回は、タイ国鉄の駅名の2回目。ローカル列車の旅気分で、車窓から見える駅名標を読み解いて行きましょう。
・タイ国鉄全664駅で多く使われている語
・水にまつわる地名
・東北線に多い หนอง [nɔ̆ɔŋ]「沼」
・แม่ [mɛ̂ɛ] 「川」は北部、คลอง [khlɔɔŋ]「運河」はチャオプラヤーデルタ
・今日のことわざ
旅ときどき単語4 駅名編(2)水にまつわる地名
タイ国鉄全664駅で多く使われている語


タイの国鉄 การรถไฟแห่งประเทศไทย [kaan rót fai hɛ̀ŋ prathêet thai/カーンロットファイ ヘェン プラテートタイ] (略称:รฟท.)、英語名 State Railway of Thailand(略称:SRT)の全駅664の駅名を分析した結果、多く使われている語のトップ10は以下のようになりました。
 บ้าน [bâan/バーン]「家・村」124駅(18.7%)
บ้าน [bâan/バーン]「家・村」124駅(18.7%)
 หนอง [nɔ̆ɔŋ/ノーン]「沼」49駅(7.4%)
หนอง [nɔ̆ɔŋ/ノーン]「沼」49駅(7.4%)
 คลอง [khlɔɔŋ/クローン]「運河」36駅(5.4%)
คลอง [khlɔɔŋ/クローン]「運河」36駅(5.4%)
- ห้วย [hûai/フアイ]「谷川・渓流」29駅(4.4%)
- บาง [baaŋ/バーン]「水流、水辺の村」26駅(3.9%)
- เขา [khău/カーウ]「山」24駅(3.6%)
- ท่า [thâa/ター]「渡し場、港」20駅(3.0%)
- วัง [waŋ/ワン]「淵、水の深い所」15駅(2.3%)
บุรี [burii/ブリー]「都市」15駅(2.3%)
นา [naa/ナー]「田んぼ」15駅(2.3%)
このうち、前回のblog028では、第1位の บ้าน [bâan/バーン]「家・村」と、それによく似た第5位 บาง [baaŋ/バーン]「水流、水辺の村」を紹介しました。今回はそれ以外を見ていきます。
※タイ国鉄の路線図および路線名については、前回のblog028を参照。
水にまつわる地名
第2位になった หนอง [nɔ̆ɔŋ/ノーン]「沼」以下、4位の ห้วย [hûai/フアイ]「谷川・渓流」、8位の วัง [waŋ/ワン]「淵、水の深い所」と、水に関する自然地名が目立ちます。11位以下では แม่ [mɛ̂ɛ/メェー] 「川」、 น้ำ [náam/ナーム] 「水」、 ปาก [pàak/パーク] 「河口」の3語がつく駅名がそれぞれ9駅ずつあります。以上6つの、水に関する語をふくむ駅名は合計119駅(2語含む駅が3駅)と、全体の17.9%をしめ、1位の บ้าน [bâan/バーン] にほぼ匹敵する多さです。
また、3位の คลอง [khlɔɔŋ/クローン]「運河」、7位の ท่า [thâa/ター]「渡し場、港」、8位の นา [naa/ナー]「田んぼ」も、水に深く関わる地名です。
言うまでもなく、タイの人々の暮らしは水と深いつながりがあります。タイ族は何世紀もかけて河谷沿いに南下し、優れた水利技術と稲作技術を生かして村や町、そして国をつくってきました。河川は交通路でもあり、生活の糧である魚を捕る場所でもありました。そんな、タイの暮らしぶりを彷彿とさせるような地名がたくさんあるのは、ある意味当然かもしれません。
さらに分析すると、これら水に関する地名と地域性との関係が見えてきて、興味深いところです。
| 路 線 | それぞれの語がつく駅数(割合) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| หนอง [nɔ̆ɔŋ] 「沼」 | ห้วย [hûai] 「谷川・渓流」 | วัง [waŋ] 「淵、水の深い所」 | แม่ [mɛ̂ɛ] 「川」 | คลอง [khlɔɔŋ] 「運河」 |
|
| 北 線 | 8(6.2%) | 6(4.6%) | 3(2.3%) | 8(6.2%) | 4(3.1%) |
| 東北線 | 23(15.0%) | 9(5.9%) | 2(1.3%) | 0(0%) | 2(1.3%) |
| 南 線 | 13(4.7%) | 11(4.0%) | 10(3.6%) | 0(0%) | 19(6.8%) |
| 東 線 | 5(7.2%) | 3(4.3%) | 0(0%) | 0(0%) | 8(11.6%) |
| メークローン線 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 1(2.9%) | 3(8.8%) |
東北線に多い หนอง [nɔ̆ɔŋ]「沼」
หนอง [nɔ̆ɔŋ]「沼」は、明らかに東北線方面が多いようです。東北線に乗ってサラブリー(สระบุร [sàràʔbùrii])駅を過ぎると、チャオプラヤー水系とメコン水系の分水嶺のドンパヤーイェン(ดงพญาเย็น [doŋpháyaayen])山地に差しかかり、列車はカーブの続く線路をあえぎながら上っていきます。峠を越えると、コーラート(โคราช [Khoorâat])高原とよばれる、標高150ー200mほどの広大な平原がメコン川まで続いています。この平原地帯をふつうイーサーン(อีสาน [iisăan])とよびますが、11月から4月ころの乾季には極端に乾燥するため、水の確保がたいへんです。そのため、沼(貯水池)が重要になるのでしょう。
หนอง [nɔ̆ɔŋ] がつく駅名をいくつか紹介します。
-
まず、沼の形状がわかるような駅名。
- หนองตม [nɔ̆ɔŋ tom /ノーントム]「泥沼」(北本線・ピッサヌローク県)
- หนองหล่ม [nɔ̆ɔŋ lòm /ノーンロム]「泥沼」(北本線・ラムプーン県)
ตม [tom] も หล่ม [lòm] も「泥」という意味です。 - หนองหิน [nɔ̆ɔŋ hĭn /ノーンヒン]「石沼」(南本線・プラチュアップキーリーカン県)
หิน [hĭn] は「石」。同じ県には有名な หัวหิน [hŭahĭn /フアヒン]「石頭」があります。
-
沼に付きものなのはやはり蓮 บัว [bua] でしょう。蓮以外の植物名がつく駅名も多いです。
- ชุมทางหนองบัว [chumthaaŋ nɔ̆ɔŋ bua /チュムターン ノーンブア]「蓮沼分岐駅」(東北本線・サラブリー県)
ชุมทาง [chumthaaŋ] は、ชุม「集まる」+ทาง「道」で路線の分岐点、分岐駅という意味です。 - บ้านหนองบัว [bâan nɔ̆ɔŋ bua /バーンノーンブア]「蓮沼村」(東北バイパス線・ロップブリー県)。これは前回のblog028でも紹介しました。
- บ้านหนองขาม [bâan nɔ̆ɔŋ khăam /バーンノーンカ-ム]「タマリンド沼村」(東北バイパス線・チャイヤプーム県)
ขาม [khăam] は มะขาม [mákhăam/ マカーム]「タマリンド」のこと。 - หนองกระจับ [nɔ̆ɔŋ kràcàp/ノーンクラチャプ]「菱沼」(東本線・プラーチーンブリー県)
กระจับ [kràcàp] は「唐菱(からびし)」や菱の仲間の植物をいいます。


(左)駅舎 (右)「泰緬鉄道起点駅」の石碑
-
沼に動物の名前がつく駅名もたくさんあります。沼には魚 ปลา [plaa]や亀 เต่า [tàu]がいますね。
- หนองเต่า [nɔ̆ɔŋ tàu /ノーンタウ]「亀沼」(北本線・ロップブリー県)
- ชุมทางหนองปลาดุก [chumthaaŋ nɔ̆ɔŋ plaadùk /チュムターン ノーンプラードゥク]「なまず沼分岐駅」(南本線・ラーチャブリー県)
- หนองปลาไหล [nɔ̆ɔŋ plaalăi /ノーンプラーライ]「うなぎ沼」(南本線・ペッチャブリー県)
ปลาดุก [plaadùk] 「なまず」は白身で淡泊、タイでよく食べられるおいしい魚です。 なまずの身をほぐしてふわっと揚げた ยำปลาดุกฟู [yam plaadùk fuu/ ヤム プラードゥクフー]、私は大好きです。ปลาไหล [plaalăi] は「うなぎ」と訳しましたが、タイで売られているのは多くが「タウナギ」だそうです。
なお、ชุมทางหนองปลาดุก [chumthaaŋ nɔ̆ɔŋ plaadùk]「なまず沼分岐駅」は、アジア太平洋戦争中に日本軍が無数の人命を犠牲に建設した泰緬鉄道の始発点です。駅には記念碑が立っています。
次の動物は、沼に出没する動物なのでしょうか。 - หนองแมว [nɔ̆ɔŋ mɛɛu /ノーンメェーウ]「猫沼」(東北ノーンカーイ線・ナコーンラーチャシーマー県)
แมว [mɛɛu] は「猫」、鳴き声から想像できますね。次の2つにはあまり会いたくありません。 - หนองกระทิง [nɔ̆ɔŋ kràthiŋ /ノーンクラティン]「野牛沼」(東北本線・ナコーンラーチャシーマー県)
- หนองเสือ [nɔ̆ɔŋ sʉ̆a /ノーンスア]「虎沼」(南ナムトク線・カーンチャナブリー県)
กระทิง [kràthiŋ] は凶暴な「野牛」、เสือ [sʉ̆a] は「虎」です。
最後に、歴史や文化を感じる沼の名前を拾ってみました。
- หนองแคน [nɔ̆ɔŋ khɛɛn /ノーンケェーン]「ケェーンの沼」(東北本線・シーサケット県)
แคน [khɛɛn] は、竹を数本束ねたタイ東北部の楽器で、日本の笙(しょう)に似ています。 - หนองคาย [nɔ̆ɔŋ khaai /ノーンカーイ]「基地の沼」(東北ノーンカーイ線・ノーンカーイ県)
メコン川に沿ったノーンカーイは、ラーマ3世時代にウィエンチャン王が起こした独立戦争を鎮圧した際、軍の基地(ค่าย [khâai/ カーイ])をおいたことで、1827年に หนองค่าย [nɔ̆ɔŋ khâai] とよばれるようになり、やがて現在名になったといいます。
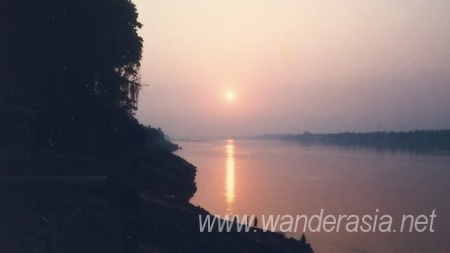

1986年撮影。対岸のラオスへはまだ、簡単には行けませんでした。
แม่ [mɛ̂ɛ] 「川」は北部、คลอง [khlɔɔŋ]「運河」はチャオプラヤーデルタ
แม่ [mɛ̂ɛ/ メェー]「川」は、แม่คลอง [mɛ̂ɛ khlɔɔŋ/ メェークローン] (メークローン線・サムットソンクラーム県)以外、みな北本線のピッサヌローク県から北、とくにプレー県、ラムパーン県、ラムプーン県といった北部タイに集中しています。川はふつう、แม่น้ำ [mɛ̂ɛnáam/ メェーナーム] ですが、北タイでは、แม่ปิง [mɛ̂ɛ piŋ/ メェーピン]「ピン川」、แม่วัง [mɛ̂ɛ waŋ/ メェーワン]「ワン川」のように、แม่ [mɛ̂ɛ] だけでよぶようです。
これに対して、ห้วย [hûai/フアイ]「谷川・渓流」、วัง [waŋ/ワン]「淵、水の深い所」は、山あいを急流が流れるイメージのあるタイ北部に多いと思っていたのですが、各路線に大きな差はありませんでした。
คลอง [khlɔɔŋ/クローン]「運河」は、チャオプラヤー川のデルタ地帯を走る、東本線やメークローン線が圧倒的に多くなります。これは予想通りでしたが、意外に多かったのが南線方面でした。南線19駅の内、チャオプラヤーデルタ地帯のラーチャブリー県までは3駅のみで、残りはマレー半島のチュンポーン県以南でした。北から見ていくと、チュンポーン県2駅、スラートターニー県6駅、ナコーンシータンマラート県3駅、トラン県2駅などです。
列車でマレー半島を南下すると、石灰岩の丘がこぶのように点在している風景が続きます。運河というイメージがなかったのですが、よくよく地図を眺めれば、スラートターニーやナコーンシータンマラートはそれなりの面積を持つ平野だと気づきました。
一方、北線や東北線方面は非常に少なくなります。石井米雄監修『タイの事典』同朋舎出版(1993年)によれば、คลอง [khlɔɔŋ] はモン語(下注参照)の「道、路」に由来することばで、中部タイのシャム語(狭義のタイ語)のみにあり、ラーオ語(東北部からラオスのタイ系の人々の言語)や北タイのムアン語(北部の旧ラーンナー王国の領域で話されている言語)にはないといいます。調べてみると、北線で คลอง [khlɔɔŋ] がつく駅は、スコータイ県の1駅以外はすべてナコンサワーン県以南のチャオプラヤー川流域に、東北線の2駅はコラート高原西端のナコーンラーチャシーマー県西部にありました。
モン人・モン語 モン人は、かつてチャオプラヤー川流域やビルマにかけて広く分布し、7世紀以降ドヴァーラヴァティーなどの国家を建て、上座部仏教を導入した。モン人の母語がモン語であり、カンボディアのクメール語と近似している。タイの地では、その後進出してきたクメール人やタイ人に征服されるが、モン人の残した文化的影響は大きい。ビルマでは18世紀までビルマ人と政治権力を競っていたが、それに敗れたモン人は大挙してタイに移住してきた。タイの王朝は彼らをチャオプラヤー川流域に住まわせ、農地開発や運河建設など重要な役割を与えた。
今日のことわざ
เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้
[sʉ̆a sɔ̆ɔŋ tua yùu thâm diau kan mâi dâi / スア ソーン トゥア ユー タム ディァウ カン マイ ダイ]
日本語訳:二頭の虎は同じ洞窟にいられない🐯🐯
「虎穴に入らずんば虎児を得ず」(出典は中国の歴史書『後漢書』)というとおり、虎は洞穴に住んでいるのでしょうか。この、タイのことわざでも、ถ้ำ [thâm] 「洞窟」が出てきます。
虎はライオンと違って単独で暮らし、狩りも自分一頭で行います。雄の方が広い縄張りを持ち、その面積は生息域が食物の豊富な南方の虎ほど狭くなりますが、それでも20ー50平方キロメートルもあるそうです。(名古屋市東山動物園のホームページによる。https://www.higashiyama.city.nagoya.jp/document/education/selfguide11.pdf)雄の虎同士が出会うと非常に激しい戦いになると言います。
そんな虎が同じ狭い洞窟にいられるわけがないですね。このことわざの意味は、虎のように力のあるものは決してライバルの存在を認めない、ということでしょうか。日本語だと(原典は『史記』のようですが)「両雄並び立たず」がぴったりと来ます。
เสือ [sʉ̆a]「虎」のかわりに จระเข้ [cɔɔrákhêe/ チョーラケー]「鰐」を使って、จระเข้สองตัวอยู่ถํ้าเดียวกันไม่ได้ [cɔɔrákhêe sɔ̆ɔŋ tua yùu thâm diau kan mâi dâi]「二匹の鰐は同じ洞窟にいられない」とも言うそうです。
[ 参考文献 ] 冨田竹二郎『タイ日辞典 改訂版』養徳社、石井米雄監修『タイの事典』同朋舎出版、岩城雄次郎・斉藤スワニー『タイ語ことわざ用法辞典』大学書林