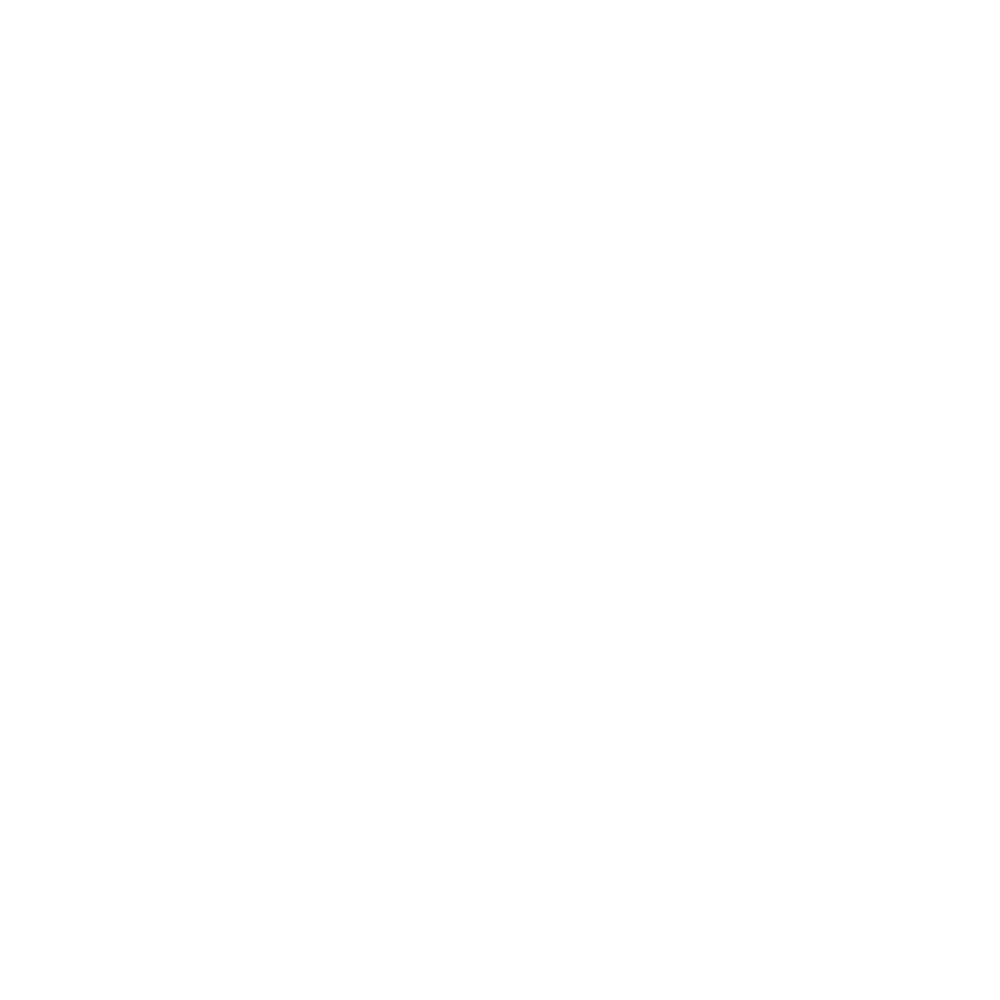旅ときどき単語3 駅名編(1)บ้าน [bâan] と บาง [baaŋ]
blog No.028 投稿日:2022.6.19(一部訂正:2022.08.12)
この記事の内容
どの言語でも語彙力が大切なのは論を待ちません。とくにタイ語は、名詞の性とか動詞の活用といった込み入った文法事項がない分、単語力がより一層重要になります。とは言っても、単語帳とにらめっこしていてもなかなか身につきませんね。
そこでこのブログでは、タイの旅行を楽しみながら単語を増やして行くという、夢のような勉強法に(あまり自信はないのですが)チャレンジしてみたいと思います。
・タイの駅名
・タイ国鉄の路線
・664駅で一番使われている語は・・・
・第1位!! บ้าน [bâan/バーン] がつく駅名
・บ้าน [bâan/バーン] と บาง [baaŋ/バーン]
・今日のことわざ
旅ときどき単語3 駅名編(1)บ้าน [bâan] と บาง [baaŋ]
タイの駅名


前2回の、blog026とblog027では、タイの77の県名(正確にはバンコク都と76県。県名は県庁所在都市名とすべて同じなので、全国77都市とも言えます。)でよく使われる語をヒントに、多くの単語を紹介しました。
ただし、やはり県名ということなのでしょうか。パーリ・サンスクリット語起源の「よそ行きで気取ったお堅い感じ」のことばが多用されています。
もっと「普段着」のことばを求めて、タイ国鉄の駅名を調べてみました。駅名には、所在地の都市名の他、途中の町や村の名前がつけられ、時には古い地名が残っていたりします。タイの鉄道、それもローカル列車の旅気分で、車窓から見える駅名標を読み解いて行きましょう。
タイ国鉄の路線
▼地図をクリックすると、拡大・縮小します。
タイの国鉄 การรถไฟแห่งประเทศไทย [kaan rót fai hɛ̀ŋ prathêet thai/カーンロットファイ ヘェン プラテートタイ] (略称:รฟท.)、英語名 State Railway of Thailand(略称:SRT)は、次の旅客線を運営しています。
路線名については、タイ国鉄のウェブサイト https://www.railway.co.th(2022年4月2日参照)では北線・東北線など5つの線名の記載があるだけで、支線など細かい名称は決まっていないようです。説明する便宜上、このブログでは【 】内のように呼ぶことにします。
- 北線 สายเหนือ [săai nʉ̆a/サーイ ヌア]
・【北本線】バンコク กรุงเทพ―チエンマイ เชียงใหม่ 751km
・【サワンカローク線】バーンダーラー บ้านดารา―サワンカローク สวรรคโลก 29km - 東北線 สายตะวันออกเฉียงเหนือ [săai tawan ʔɔ̀ɔk chĭaŋ nʉ̆a/サーイ タワンオークチエンヌア]
・【東北本線】バーンパーチー บ้านภาชี―ウボンラーチャターニー อุบลราชธานี 485km
・【ノーンカーイ線】タノンチラ ถนนจิระ―ノーンカーイ หนองคาย―ターナーレーン ท่านาแล้ง(ラオス)361km
・【東北バイパス線】ケンコーイ แก่งคอย―ブアヤイ บัวใหญ่ 251km - 南線 สายใต้ [săai tâi/サーイ タイ]
・【南本線】トンブリー ธนบุรี―スガイコーロク สุไหลโก-ลก 1,143km
・【バンスー線】バンスー บางซื่อ―タリンチャン ตลิ่งชัน 15km
・【スパンブリー線】ノーンプラドゥク นองปลาดุก―スパンブリー สุพรรณบุรี 78km
・【ナムトク線】ノーンプラドゥク นองปลาดุก―ナムトク น้ำตก 130km
・【キーリーラッタニコム線】バーントゥンポー บ้านทุ่งโพธิ์―キーリーラッタニコム คีรีรัฐนิคม 31km
・【カンタン線】トゥンソン ทุ่งสง―カンタン กันตัง 93km
・【ナコーンシータンマラート線】カオチュムトーン เขาชุมทอง―ナコーンシータンマラート นครศรีธรรมราช 35km
・【パーダンベーサー線】(マレー鉄道連絡線)ハートヤイ หาดใหญ่―パーダンベーサー ปาดังเบซาร์ 45km
- 東線 สายตะวันออก [săai tawan ʔɔ̀ɔk/サーイ タワンオーク]
・【東本線】バンコク กรุงเทพ―バーンクローンルック国境駅 ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก 260km
・【バーンプルータールアン線】チャチューンサーオ ฉะเชิงเทรา ―バーンプルータールアン บ้านพลูตาหลวง 123km
- メークローン線 สายแม่กลอง [săai mɛ̂ɛ klɔɔŋ/サーイ メークローン]
・【マハーチャイ線】ウォンウィエンヤイ วงเวียนใหญ่―マハーチャイ มหาชัย 31km
・【メークローン線】バーンレーム บ้านแหลม―メークローン แม่กลอ 34km
日本より広いタイの隅々まで線路があるわけではありませんが、それでも東西南北各方面に、総計4,070kmもの路線を持っています。駅の数は、全部で664。その駅名を分析してみました。
(注)距離や駅について
・Wikipedia の รายชื่อสถานีรถไฟ สายเหนือ, รายชื่อสถานีรถไฟ สายตะวันออกเฉียงเหนือ, รายชื่อสถานีรถไฟ สายใต้, รายชื่อสถานีรถไฟ สายตะวันออก, ทางรถไฟสายแม่กลอง に基づいています。(2022年4月2日参照)
・タイ国鉄のウェブサイト https://www.railway.co.th(2022年4月2日参照)では、例えばバンコク―チエンマイ間の距離について、「歴史」のページでは752.077km、「運賃検索」のページでは751kmとなっています。詳細は不明ですが、鉄道建設としての距離と現在の運用距離の違い(あとでバイパス工事をすれば距離は縮まる)などが原因かと思われます。駅名についても、タイ国鉄のウェブサイト「時刻検索」のページでは689駅ありましたが、検索しても停車する列車がない駅も散見されました。
664駅で一番使われている語は・・・


664の駅名で多く使われている語のトップ10を発表します。
 บ้าน [bâan/バーン]「家・村」124駅(18.7%)
บ้าน [bâan/バーン]「家・村」124駅(18.7%)
 หนอง [nɔ̆ɔŋ/ノーン]「沼」49駅(7.4%)
หนอง [nɔ̆ɔŋ/ノーン]「沼」49駅(7.4%)
 คลอง [khlɔɔŋ/クローン]「運河」36駅(5.4%)
คลอง [khlɔɔŋ/クローン]「運河」36駅(5.4%)
- ห้วย [hûai/フアイ]「谷川・渓流」29駅(4.4%)
- บาง [baaŋ/バーン]「水流、水辺の村」26駅(3.9%)
- เขา [khău/カーウ]「山」24駅(3.6%)
- ท่า [thâa/ター]「渡し場、港」20駅(3.0%)
- วัง [waŋ/ワン]「淵、水の深い所」15駅(2.3%)
บุรี [burii/ブリー]「都市」15駅(2.3%)
นา [naa/ナー]「田んぼ」15駅(2.3%)
第1位!! บ้าน [bâan/バーン] がつく駅名
ご覧の通り、最も多かったのは บ้าน [bâan/バーン] でした。664駅中124駅(18.7%)、およそ5駅に1駅はこの語がつきます。2位以下に圧倒的大差をつけました。とくに東北線では、153駅中41駅(26.8%)と1/4以上を占めました。
บ้าน [bâan] は、「家」「住むところ」を意味します。หมู่บ้าน [mùu bâan/ムーバーン] 「村」という意味でも使われます。หมู่ [mùu] 「群れ、グループ」+ บ้าน [bâan] 「家」で、家が集まっている所が村というわけです。村がやがて大きくなって町になっても、บ้าน [bâan] という地名を残すことが多いそうです。


意味が容易に類推できる駅名をいくつか挙げてみます。
- บ้านใหม่ [bâan mài /バーンマイ](北本線・ピッサヌローク県)「新村」。ใหม่ [mài]「新しい」。
これに対して、 - บ้านเก่า [bâan kàu /バーンカウ](ナムトック線・カーンチャナブリー県)「旧村」もありました。เก่า [kàu] は「古い」。
- บ้านนา [bâan naa /バーンナー](南本線・スラーターニー県)「田村」。นา [naa] 「田」。
一方、 - บ้านไร่ [bâan râi /バーンライ](ノーンカーイ線・ナコーンラーチャシーマー県)「畑村」もあります。ไร่ [râi] は「畑」のこと。
植物の名前がつく例も散見されます。
- บ้านไผ่ [bâan phài /バーンパイ](ノーンカーイ線・コーンケン県)「竹村」。ไผ่ [phài] は「竹」。
- บ้านกล้วย [bâan klûai /バーンクルアイ](南本線・ラーチャブリー県)「バナナ村」。กล้วย [klûai] は「バナナ」です。
- บ้านหนองบัว [bâan nɔ̆ɔŋbua /バーンノーンブア](東北バイパス線・ロップブリー県)「蓮沼村」。หนอง [nɔ̆ɔŋ] 「沼」、บัว [bua] 「蓮」の意味です。หนอง [nɔ̆ɔŋ] がつく駅名も49駅(7.4%)と非常に多く、第2位になります。
他におもしろいものを少しあげてみます。
- บ้านขอม [bâan khɔ̆ɔm /バーンコーム](マハーチャイ線・サムットサーコーン県)「カンボジア村」。ขอม [khɔ̆ɔm] は「カンボジア」を意味します。カンボジア人が入植した(あるいは、戦争などで連行され、入植させられた)のでしょうか。
- บ้านด่าน [bâan dàan /バーンダーン](北本線・ウッタラディット県)「関所村」。ด่าน [dàan] は「関所、検問所」など、人や物をとどめて検査する場所のことです。この村は地図で見ると、ウッタラディット県の北で、北タイ(ラーンナー)との国境地帯だったのでしょうか。
- บ้านค่ายไทย [bâan kâai thai /バーンカーイタイ](南本線・パッタルン県)「タイ軍駐屯村」。ค่าย [kâai] 「駐屯地、軍のキャンプ」です。ここはマレー半島の深部、マレーシア(イスラーム諸王国)との境界です。
- บ้านพระพุทธ [bâan phráphút /バーンプラプット](東北本線・ナコーンラーチャシーマー県)「仏村」。พระพุทธ [phráphút] は「仏陀」「仏様」。よほど村人の信心が篤かったのでしょうか。
บ้าน [bâan/バーン] と บาง [baaŋ/バーン]
บ้าน [bâan/バーン] とよく似た語に บาง [baaŋ/バーン] があります。บาง [baaŋ] がつく駅名も全部で26駅(3.9%)と結構多くあって、全体では5位に入っています。
この2つの語は、発音も意味も似ています。発音は、日本語で表記すると同じ「バーン」になってしまいますが、最後の子音 [-n][-ŋ] と、声調が違うので、区別できるようにしましょう。บ้าน [bâan] の意味は「村」「集落」ですが、บาง [baaŋ] の意味もほぼ同じです。では、違いはどこにあるのでしょうか?
タイで権威のある王立学士院 ราชบัณฑิตยสถาน [râtchábandìttàyásàthăan/ラーチャバンディッタヤサターン] の辞書(仏暦2554年版、https://dictionary.orst.go.th)によると、บาง [baaŋ/バーン] は「(川や海に流れ込む)水の小さな流れに沿った、またはかつて沿っていた集落、あるいはかつて水の小さな流れがあった場所に位置する集落」とあります。
そういう視点で見ると、おもしろいことに気づきます。บาง [baaŋ] がつく駅名が、路線の駅数比で一番多いのはメークローン線(34駅中5駅、14.7%)、次に東線(69駅中5駅、7.2%)となります。いずれの路線も、タイ湾に近く、細かい川の流れや運河が張り巡らされている地域を走ります。これに対して、比較的雨量の少ないコーラート高原を貫く東北線では、บาง [baaŋ] がつく駅名が一つもありませんでした。
| 路 線 | บ้าน [bâan] がつく駅数(割合) | บาง [baaŋ] がつく駅数(割合) |
|---|---|---|
| 北 線 | 19(14.6%) | 5(3.8%) |
| 東北線 | 41(26.8%) | 0(0.0%) |
| 南 線 | 46(16.5%) | 11(4.0%) |
| 東 線 | 11(15.9%) | 5(7.2%) |
| メークローン線 | 7(20.6%) | 5(14.7%) |


ちなみに、首都バンコクの「バン」も บาง [baaŋ] です。(だから、英語表記は Bangkok なんですね。)アユッタヤー朝時代には、บางกอก [baaŋ kɔ̀ɔk/バーンコーク] とよばれていました。กอก [kɔ̀ɔk] は มะกอก [mákɔ̀ɔk/マコーク](木の名。枇杷ほどの大きさの実がなり、食べられる)の短縮形で、「マコークの木のある水辺の村」という意味になります。1782年に王都となると、กรุงเทพมหานคร [kruŋ thêep mahăa nakhɔɔn/クルンテープ マハーナコーン] と改名されましたが、外国人は บางกอก [baaŋ kɔ̀ɔk] Bangkok とよび続け、今に至っています。なお、บางกอก [baaŋ kɔ̀ɔk] の名称は、バンコク都の区名や運河名の、บางกอกใหญ่ [baaŋ kɔ̀ɔk yài]、บางกอกน้อย [baaŋ kɔ̀ɔk nɔ́ɔi] として現在も残っています。
今日のことわざ
ปล่อยเสือเข้าป่า
[plɔ̀i sʉ̆a kâu pàa / プロイ スア カウ パー]
日本語訳:虎を放って森に帰す
ปล่อย [plɔ̀i] は「解き放つ」という意味です。お寺に行くと、竹製の小さな籠に入れられた小鳥や、バケツに入った魚が「売られて」います。これは、ปล่อยนก ปล่อยปลา [plɔ̀i nók plɔ̀i plaa /プロイ ノック プロイ プラー] といって、お金を出して買い取り、小鳥や魚を自由にしてやることで徳を積む(タイ語で ทำบุญ [tham bun /タム ブン] といいます)のが目的です。いわゆる放生(ほうじょう)ですね。近年、お寺の境内では、動物虐待につながるので小鳥を「買わ」ないでという注意書きがあったりします。捕まっていた小鳥は弱ってしまうので、放たれてもまた捕まってしまうようです。
解き放った小鳥や魚が恩義を感じてくれるかはわかりませんが、表記の言い回しは、凶暴な虎は放しても恩義に感じるどころかまた暴れる、という意味です。敵や犯罪者を逃がせば、災難がまたやってくるという、きわめてリアリスティックな考えを表しています。続けて、ปล่อยปลาลงนํ้า [plɔ̀i plaa loŋ náam /プロイ プラー ロン ナーム] 「魚を放って水に戻す」という句を続けることもあります。ということは、放生で解き放った魚も恩義を感じないとタイ人は考えているのでしょうか。
[ 参考文献 ] 冨田竹二郎『タイ日辞典 改訂版』養徳社、岩城雄次郎・斉藤スワニー『タイ語ことわざ用法辞典』大学書林
このほかに、文中にあるウェブサイトを参照しています。