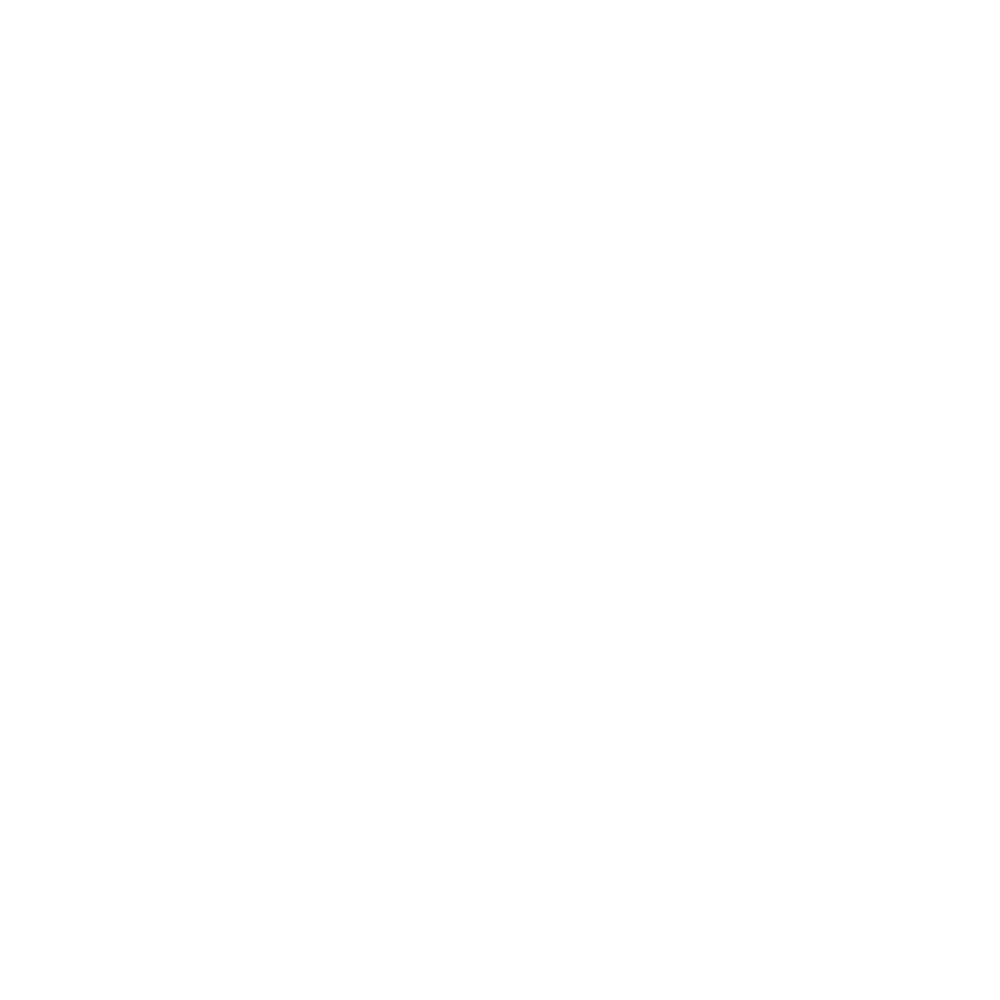タイ文字講座 STEP9 子音字の連続(3) [-a] を入れて読む
blog No.021 投稿日:2021.1.12 /一部修正:2021.7.11
この記事の内容
複雑怪奇に見えて取っ付きにくいけど、どことなくユーモラス。このタイ文字の基本的な読み書きができるようになりましょう。タイ文字の習得はタイ語学習の大きな「ヤマ」です。
子音字が連続するときの発音パターンを3回にわたって見てきました。今回が最終回。ここをクリアするとかなり文字が読めるはずです。
・子音字が連続するときの発音
・(d) 最初の子音字のあとに [-a] を入れて発音するパターン
・(d-1) 第二子音字の音節が第一子音字の声調に従うパターン(第一子音字が引字となる)
・(d-2) 第二子音字の音節が第二子音字の声調に従うパターン
・インド由来の語
・「習うより慣れろ」と言うけれど...
・【問題】正しい発音で読んでみましょう
・過去の関連記事
・今日のことわざ
STEP9 子音字の連続(3) [-a] を入れて読む
子音字が連続するときの発音
前々回の blog019 で説明したように、語頭から子音を表す文字が連続するときの発音は、次の4パターンになります。
(a)最初の子音字のあとに [-o-] を入れて発音するパターン
(例)กบ [kòp /コップ]「蛙」
※blog014 で学習しました
(b)実際に二重子音として発音するパターン
(例)กลาง [klaaŋ /クラーン]「真ん中」
กล- を [kl- /クル] と連続した子音(二重子音)で発音します。
※前々回の blog019 で学習しました
(c)実際には単独の子音として発音するパターン
(例)สระ [sàʔ /サッ]「池」
二番目の子音字 ร [r] は、実際には発音しません。(発音しない文字を黙字と言います)
※前回の blog020 で学習しました
(d)最初の子音字のあとに [-a] を入れて発音するパターン
(例)สนาม [sànăam/ サナーム]「広場」
一番目の子音字 ส [s] のあとに [-a] を加えて、後半の音節 นาม [naam] につなげます。
※今回の blog021 で学習します
(d) 最初の子音字のあとに [-a] を入れて発音するパターン
(d)の母音 [-a] を挿入して発音するパターンは、第二子音字の音節の声調をどの文字が決定するかによって、さらに2つのパターンに分けられます。
(d-1)第一子音字 + [-a] + 第二子音字の音節(声調は第一子音字に従う)
(d-2)第一子音字 + [-a] + 第二子音字の音節(声調は第二子音字に従う)
※[-a] は、本来は [-aʔ] (もっと正確に言えば、声調をともなって [-àʔ]、[-áʔ] )と表記すべきですが、実際の発音でははほとんど消えますので、 [-ʔ]は省略しました。下の注(音節の軽声化について)もご覧ください
※(d-1)(d-2)の見分け方については、あとの項目で説明します。
(d-1) 第二子音字の音節の声調が第一子音字に従うパターン(第一子音字が引字となる)
(d-1)のパターンは、前回のblog020の(c-2)第一子音字の อ, ห を読まないパターン(引字の อ と ห )とよく似ています。ただし、第一子音字は母音 [-a] をつけて発音します。すなわち、
・第一子音字の中子音字(ก, จ, ต, บ, ป, อ)は母音 [-a] をつけて発音し、引字として働いて第二子音字を中子音字に変える
・第一子音字の高子音字(ข, ฉ, ถ, ผ, ฝ, ส)は母音 [-a] をつけて発音し、引字として働いて第二子音字を高子音字に変える
・第二子音字は低子音字単独字(ม, ง, น, ณ, ร, ล, ฬ, ย, ญ, ว の10個の文字)に限られる
このように、第一子音字が第二子音字の低子音字を中子音字や高子音字に変えることでその声調を支配します。この働きをする文字を引字といいます。
例を見てみましょう。
(1)中子音字化の例
・ตลาด 「市場」……[tà-làat](または [ta-làat] ※下の注を参照)
第一子音字の中子音字 ต が引字として働くので、第二子音字 ล が中子音字化されます。したがって、
ต [tà] -ลาด [làat] となります。
同様の例をいくつかあげておきます。
・จมูก [càmùuk]「鼻」
・ตลิ่ง [tàlìŋ]「岸」
・อร่อย [àʔrɔ̀ɔi]( [àʔrɔ̀i]と発音することが多い)「おいしい」
(2)高子音字化の例
・ขนม 「菓子」……[khà-nŏm](または [kha-nŏm] ※下の注を参照)
第一子音字の高子音字 ข が引字として働くので、第二子音字 น が高子音字化されます。したがって、
ข [khà] -นม [nŏm] となります。
同様の例をいくつかあげておきます。
・ฉวาด [chàlàat]「賢明な」
・ถนน [thànŏn]「通り、道」
・สนุก [sànùk]「楽しい」
実際には、第一子音字 + [-a] の音節は軽く発音されることが多いです。つまり、本来の声調どおりではなく、軽く平声(普通声調)で発音されます。紛らわしくなければなるべく楽に発音するようになるというのは、どの言語でもごく当たり前に起きている現象です。
今回のblogでは、声調規則の説明をしているので、本来の声調と( )内には軽声化された発音を並べて書きましたが、これ以外の、声調がとくにテーマではない部分では、実際の発音に従って声調を省いた部分が多いです。声門閉鎖音 [-ʔ] については省略してあります。ただし、学習書によっても表記に差がありますので、ご留意ください。
(d-2) 第二子音字の音節の声調が第二子音字に従うパターン
前項を要約すると、(d-1)のパターン、つまり第一子音字が引字として働いて第二子音字を中子音化または高子音化するのは、
・第一子音字が、中子音字または高子音字であること
・第二子音字が、低子音字単独字であること
という2条件がそろった時だということです。
逆に言えば、この2条件がそろわない時は、すべて(d-2)のパターン、第一子音字は第二子音字の声調に影響しないということです。つまり、単純に [-a] を入れて発音すればよいのです。
例をあげてみます。
(1)สบาย 「快適だ」……[sà-baai](または [sa-baai] ※前項の注を参照)
第一子音字の ส が引字に見えるので、第二子音字を高子音化して [×] [sabăai] と読みたいところです。しかし、第二子音字 บ が低子音単独字ではなく中子音字なので、 ส は引字とならず、あとの子音字に影響しません。したがって、
ส [sàʔ] - บาย [baai] となります。
(2)เฉพาะ「とくに、~だけ」……[chà-phɔ́ʔ](または [cha-phɔ́ʔ] ※前項の注を参照)
これも一見、第一子音字の ฉ が引字に見えますが、第二子音字 พ が低子音単独字ではなく低子音字対応字(同じ発音の文字が高子音字にある= ผ )ので、ฉ は引字とならず、あとの子音字に影響しません。したがって、
ฉ [chà] - เพาะ [phɔ́ʔ] となります。
なおスペルは ฉเพาะ ではなく、母音符号 เ-าะ で全体を挟むように書きますので注意してください。
(c)ทหาน「軍、兵士」……[thá-hăan](または [tha-hăan] ※前項の注を参照)
第一子音字の ท が低子音字なので引字ではありません。したがって、
ท [thá] - หาน [hăan] となります。
インド由来の語
タイ語には、インドのパーリ語・サンスクリット語に由来する単語が非常に多く取り入れられています。これらの語の場合、原則として(d-2)のパターン、つまり、
第一子音字 + [-a] + 第二子音字の音節(声調は第二子音字に従う)
で発音します。例えば、
(1) สมาคม「協会」…… [sà-maa-khom](または sa-maa-khom] ※上の注を参照)
(d-1)のルールならば、第一子音字の高子音字 ส が引字として働くので、[×] [sà-măa-khom] と読むのですが、この語はパーリ・サンスクリット語に由来するため、(d-2)のパターンで読みます、
(2) ขมา「罪を認めて謝る」……[khà-maa](または [kha-maa] ※上の注を参照)
(d-1)のルールならば、第一子音字の高子音字 ข が引字として働くので、[×] [khà-măa] と読むのですが、この語はパーリ・サンスクリット語に由来するため、(d-2)のパターンで読みます、
ところが例外も多く、(d-1)のパターン、つまり、
第一子音字 + [-a] + 第二子音字の音節(声調は第一子音字に従う)
と発音する語もあります。パーリ・サンスクリット語起源でありながら、汎用された結果、純タイ語に準ずる扱いをされ、純タイ語の声調規則で発音されるようになったと考えられます。例えば、
(3) ศาสนา「宗教」……[saàt-sà-năa]
後半の สนา に注目すると(d-1)のパターン、つまり、高子音字 ส が引字として働くので、[-năa] と上声(第4声調)で発音します。
(4) ผลึก 「水晶」……[phà-lʉ̀k]。(または [pha-lʉ̀k] ※上の注を参照)
この単語については、blog019 インド由来の語は二重子音ではなく [-a] をはさむにおいて、声調の例外として紹介しました。
「習うより慣れろ」と言うけれど...
3回にわたって、子音字が連続する場合の発音について、説明してきました。
しかし、文字の並びだけを見てどのパターンで読むのか判別するのは難しく、例外もあるので、すべて法則的に理解するのは困難です。おそらくタイ語ネイティブには、このblogで説明したようなパターンにあてはめて、どう読むかを判断している人はいないと思います。耳で聞いて知っていることばと、文字で書き表されたことばが、頭の中で自然と一致するものではないでしょうか。私たち、日本語ネイティブが日本語の文字をどう読んでいるかを考えれば容易に理解できますね。
しかしながら、タイ語のボキャブラリーが十分でないタイ語非ネイティブにとっては、このblogで説明したような法則性やパターンを理解することが、上達のための第一歩となるはずです。おおよその理解ができたら、あとはそれぞれの単語の発音を、文字のスペルを見ながら覚えていきましょう。
「習うより慣れろ」とよく言われますが、やはり、最初は「習う」べきです。そして、「習う」ことがだいたいできたら、(ここが大切なのですが、「だいたい」で十分で、「完璧」な習いを求めてはいけません。)「慣れる」ことに軸足を移していくのが、上達の近道だと思います。
【問題】正しい発音で読んでみましょう
正しいと思う〇をクリックしたあと、確認ボタンを押してください。
インド由来の例外的な単語はありません。上の(d-1)(d-2)どちらのルールに当てはまるか判断してください。なお、第一子音字 + [-a] の音節についても、軽声化する前の本来の声調を書いておきました。